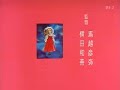1Q84 BOOK 3
雑誌に特集が組まれ、謎解き本が出版されなど、何かと話題の本作だが、
いくら細かく切り刻んだり結びつけたりしてもこの本がなぜこれだけ人気なのかを
説明できているわけではないと私は思う。
これまでのレビューにあるように、女性の体の描写に不快感を抱く読者がおり、
文学の死を叫んだり、社会に対して襟を正せとどなったり、宗教を分かってない
などとこき下ろしたりとさまざまだが、この作品に求めているものが読者によって
異なっているということだろう。
レビューにとらわれずに読んで、楽しんでほしいと私はお薦めする。★5つの
レビューが参考にならなかったと切り捨てられることが多くとも、あえて減点無し
でお薦めしたい。迷っているのなら読んでみたらどうだろうか。
この小説は創作であり、著者が有名だからという理由で比較対象とされる現実の
物事に対する配慮や正確性を求められる必要はない。性的な表現もいつもの村上氏
の味だ。主人公はクリーンである必要はなく、対抗する宗教団体も「悪の組織」で
なければならない理由はない。読む側がそこに個人的な規範を持ち込むから、その
ように不ぞろいな反応が起こるのだ。
あわせて千数百ページの長編を概観することは不可能だが、この物語を通して
作者が語りたかったことのひとつはこうだと想像する。現実社会が実は曖昧で不安定
であり、人々は揺るがない(ように見える)枠に自ら入り込んで生きたがり、その中
で正しいと思われた価値観が、枠の外では反社会的であったり、違法であったりする。
それを描くことで、人々は社会の成り立ちの不確かさや目に見える物事の裏に隠された
「深み」に思いをはせることができる。文学的であることは、公平公正で正義を身に
まとい、理想を標榜することとは無関係だ。まして、勧善懲悪的な構図やスリルを
演出することとも違う。
ストーリーに入り込んで楽しめたこと以外に私が面白いと思ったのは、著者本人の
ものと思われる哲学的な認識が登場人物によって語られていることろだ。特にBook1の
第22章にある「時間と空間と可能性の観念」を人間が脳の発達によって獲得したと
いう記述とそれに続く説明については私の考えに近く、納得したところだ。
全体を通してヤナーチェック作曲の「シンフォニエッタ」が登場する。この曲を私は
高校の頃、実際に演奏したことがある。Book1の冒頭にこの曲が登場したとき、その
重厚な響きを頭の中で蘇らせることができたことも、この小説に入り込むことができた
要因のひとつだろうと個人的に思っている。もちろん、この作品に登場するいかなる
曲や文学作品に触れたことがなくても、ストーリーを、とりあえず目の前に広がった
現実として読み進めれば、最後まで飽きることなく読み通してしまうことだろう。
小説は解釈より「ノメリコミ」が大切!読み進めている最中の気持ちが大事だ。
ストーリーを追体験してつかの間の楽しみを得るためにこそ小説は読まれるべきだと
私は思う。
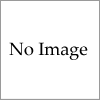
Sports Graphic Number Do号 100人が語るRUN!
村上春樹インタビュー、Q&Aという豪華な特集や、直近に行われた表参道レースや東京マラソンの情報を網羅している。また、芸能人から一般ランナーまで100人の「走る」コメントを掲載。非常に読み応えある一冊。

トニー滝谷 プレミアム・エディション [DVD]
今作はロッテルダム国際映画祭で二つの賞を獲った、とるべきのすばらしい完成度の高い秀作である。まず讃えるべきは市川準の静かな演出も然ることながら、撮影の芸術性に目は向けられるのだ。撮影の広川泰士は写真家であるということ。まずその新鮮な事実に驚愕したが、やはり、というべき素晴らしい構図とカメラワークは完璧で、この人が作品を作ったと言っても大袈裟な表現ではない。撮影者がだれであるかは難儀の孕んだ問題なのである。スコセッシならば撮影は「マイケルチャップマン」、という相互のセンスがフィルムの中で、完全的に合致している。それ故に市川と、広川の作品をもっと観てみたいものである。とにかくモノトーンのその静的な世界は無機質な美しさ、そして様子を余すことなくやわらかく映し出している。そしてまたイッセー尾形は淡々としながらも奇妙な存在感を見せ、傑出的に演じて見せている。宮沢りえの巧さは言うまでもなく迷いは、一切決してない。また音楽は坂本龍一が鳴らしているが、無機で苦く静寂感に満ちており、重厚感さえもそこに存在している。ゆっくりと、映画を誘導し、物語の深みを帯びさせた。
孤独に、一人に生きてきた男がある日、女性に会い好きになった。しかし彼女は交通事故で亡くなってしまう。そして彼は彼女のことが忘れられなかった。万年孤独だった彼が愛を見つけ、いつかその人が死に孤独の身へと落ちていく。孤独でも何とも感じず、当たり前だと生きてきた長い時には及ばぬ愛を求める心が生まれていく。そして彼は人間の業深き、愛へと向かっていく。その時、に知った類まれな愛の欠落は、人間に苦しみを与える。ラストシ−ン、業火で焦げ、破った一枚のの写真に彼は消化し得ない解決を見出そうとした。
その無常な苦しみ、灰色の入道雲は心から二度と離れずに悲哀に溢れて止まらないのである。

Norwegian Wood
英語もとても読み易いし、背景が日本なので、英語を学習している人にもお薦めです。何より、描写がみずみずしくて、また、ちょっとだけ、現実ばなれしていて、面白いです。同じ作者の「ネジまきクロニクル」も合わせて読みましたが、こちらこちらで昭和史含みで、面白いのですが、「ノルウェイの森」の方が、スピード感があるし、若々しいので、こちらの方がお気に入りです。また、人の心の掘り下げかたもこちらの方が深いように思います。

ベートーヴェン:大公トリオ
戦前、世界最高の技量をもつ演奏家を揃えた百万ドルトリオ(ルービンシュタイン、ハイフェッツ、フォイアマン)による歴史的演奏。チェリストのフォイアマン(Emanuel Feuermann:1902-1942)は、ツィゴイネルワイゼンをチェロで弾くことで知られる超絶技巧のチェリストであるが、この演奏の録音(1941年)の翌年に夭折してしまった(その後百万ドルトリオはピアティゴルスキーがチェリストとなって続けられた)。
演奏は技術的には非の打ち所がないが、それぞれが強烈な個性をもった演奏家であるためアンサンブルとしては問題もないではない。かつて1920年代の後半に録音されたカザルストリオ(コルトー、ティボー、カザルス)のほうがはるかに成功していると思う。しかしそうはいうものの、これだけの歴史的名手を揃えた演奏はめったになく、歴史的演奏として手元においておきたい演奏である。