
三つのブランコの物語 (講談社漫画文庫 は 3-15)
自分にとってはまさに原点です。懐かしい記憶につられて読んでみました。
とりわけ第1話の「カトリーヌの章」は、こんな幸せな恋がしたいなぁ、と夢見ていた少女時代を思い出します。
子供の頃感動したものは、いくつになっても愛着があるものですね。
少女まんがはさまざまに分野が増えて、名作もたくさん生まれたけれど、こういう懐かしさは他では味わえません。
表紙の装丁も「いかにも」という感じで、あの頃を思い出させました。

きまぐれオレンジ☆ロード Loving Heart
このアルバムこそ、幾多のアニソンアルバムの最高峰だと思う
思い出補正を差し引いても全然余る
30代の自分は当時リアルタイムで漫画、アニメを観ていた口で
始めて、秋葉原でCDを購入したのも、このアルバム
今のように、ネットショッピングが盛んではなかった時代
地元ではどうしても手に入れる事が出来なかった
その為、一路秋葉原へと訪れたのが、全ての始まりであり
後に延々と続く、おたく道へと邁進して行く
レビューには成らないので、此方に記している
今の若い人達が聴いたら
果してどう感じるのだろうか?
古臭い? それとも時代遅れ? ダサ杉?
別にそれでも構わない
自分達は80年代を懸命に駆け抜け
そして、今この瞬間も懸命に駆け抜けている
アニソンの枠なんてそんな物
とっくに超越して居る!
このアルバムは
『オレンジロード』と言う新しいジャンル何だ
決して唯のアニソン等ではない!
超能力なんて始めから要らなかったんだ
初めて逢ったときから
今もずっと、そしてこれからも
俺達そして、みんなの
『永遠の夏は終わらない』

伝説のピアニスト
石川康子さんの書いた「原智恵子 伝説のピアニスト」を読んで原(1914-2001)のことを知り、「聴いてみたいなあ」と思っていたところへちょうど発売された、うれしいCD。
ショパンの協奏曲は1962年12月、東京・世田谷区民会館でのライブ・ステレオ録音。
たっぷりと、ふくらみのある響きが伝わってくる非常に優れた録音である。原の演奏は、この曲の持つ夢見るようなロマンチシズムと青春の激しさの両面をあわせもった名演で、聴く者を飽きさせない。
ドビュッシーは1959年ごろのステレオ録音(教材用)、ショパンは1937年録音のSP盤(フランス・HMVレーベルによる原のデビュー盤。もちろんモノーラル)からの復刻。
文化放送の技師としてショパンの録音を直接担当した若林駿介氏(音楽評論家)による「この録音について」というノートが付いていて、これが貴重。「解説」(濱田滋郎氏)によると、若林氏はこの録音テープを日フィルの倉庫から探し出したという。若林さん、ありがとう。

きまぐれオレンジ☆ロード The Series テレビシリーズ DVD-BOX
赤い麦わら帽子に始まり、赤い麦わら帽子で終わる。最高のラブストーリーだったと思います。もうずいぶん時間が経ってしまっていて、今となれば、その頃の思い出がぼやけてます。昔の記憶に会いたくて、今回DVD-BOXを購入してみようと思いました。
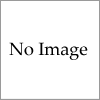
原智恵子 伝説のピアニスト (ベスト新書)
原智恵子は、幼いころから単身でヨーロッパに渡り、
研鑚を積んだ経験から、勝気で大陸的な性格を持ちあわせていました。
当時の日本人女性として求められた奥ゆかしさ、控えめな性格でないことを理由
に(あるいは、あるひとりの男性の嫉妬を理由に)、日本の音楽界からは次第に
「抹殺されていく」運命にありました。
(どんなに、ヨーロッパ(パリ)で、輝かしい功績をおさめようが、素晴らしいプレイ
ヤーであろうが)
同時期に、比較対照としての存在として現れたのが、「安川加寿子」でした。
「原智恵子」を知らなくても、「安川加寿子」なら大方の人が知っている、
という事実こそ、当時のそして今日まで続く、「音楽業界の闇」を物語っているのです。
本の後半。
愛する二人の息子と離れ、20歳年上のチェリスト「ガスパール・カサド」と再婚し、
彼が亡くなるまでのわずか8年間の充実した音楽家生活、そして彼と過ごした思い出
深いフィレンチェを出、日本に戻って、ひとり老人施設で生活し、亡くなるまでの様子。
その克明な描写に心打たれました。
「芸術」への志を曲げずに生きようとした、ひとりの音楽家の女性の半生を、戦中戦後の
文化の発展過程を背景に知ることの出来る、重みのある本でした。






