
「死の棘」日記 (新潮文庫)
遂に出撃命令の出なかった特攻隊長だった著者島尾敏雄の、戦後10年目の平和日本社会での凄惨な夫婦生活の記録である。
毎朝、妻(ミホ)の反応を見極めることから著者(僕)の一日が始まる。かつての僕の不倫は、ミホの精神に決定的な傷痕となって深く残っている。その棘の傷が疼かないように祈るしかない僕が、およそ離婚などという当世風の逃避を思いつくことすらなく、ただただミホの攻撃に耐える毎日の記録を読むと、人を裏切ることを知らなかったミホの純真さが哀切に迫ると共に、やはり、最後に真の情愛を交わせるのは、夫婦という他人同士しかないのだろうか、という思いを抱かせられる。
そして膨大な日記の中で、時折訪ねてきたり便りをくれる、吉行淳之介、奥野健男、吉本隆明、庄野潤三などとの交友部分は束の間の涼風のようにホッとする時間である。

死の棘 (新潮文庫)
この小説の凄さは多くのレビュアの方に語り尽くされている。兎に角、ひたすらどろどろの世界が続く。これほど凄まじい関係性が描かれた作品は唯一無二と言ってもいいかもしれない。そして僕が驚くのはこの現実を抱えながら、その状況を小説化できた島尾敏雄の客観性といい意味でのしたたかさだ。通常これだけの狂気を抱えた状況では家族はほぼ確実に潰される。昨今は「介護うつ」といった言葉も広まっているが、そんなものでは済まないだろう。
作品はひたすらに妻の狂気が続く。しかし、この作品はその壮絶さの温度を伝えながら圧倒的な面白さで進む。
そして何処にも救いは、無い。

IN
桐野夏生の小説には、読むとすぐにそれとわかるモデル事件が存在する。
『OUT』の井の頭公園バラバラ死体遺棄事件、『グロテスク』の東電OL殺人事件、『東京島』のアナタハン事件。
そして本作は、島尾敏雄夫妻と敏雄の作品『死の棘』、業界では誰もが知っていた作者自身のダブル不倫事件がモデルとなっている。
現実に題材を取る作家ではあるものの、しかし桐野は現実に取材する作家ではない。
本作の感想に、作家の取材方法がわかって面白かったと表現しているものを散見するが、桐野自身はこの手のインタビュー取材を行ってはいないのだ。島尾敏雄とミホ夫妻に対する子供側からの冷ややかな視線は、島尾伸三本人が、すでに赤裸々に綴っているところであり、桐野はそれを読んだだけであることは明らかである。
つまり、物語の後半、劇的に真相が明かされていく過程は、娯楽小説としてのスタイルであり、桐野の創作なのだ。もちろん、彼女の不倫相手も死んではいない。
娯楽としてのサービスが充分であり、巧いとも言えるが、甘いともいえる。
良くも悪くも、本作は『OUT』の裏面、対になる作品であり、『OUT』が最終局面で甘く緩い方角に流れたように、また作者のデビュー作の特徴である、「主人公だけに、とっておきの秘密をべらべらと喋る初対面の相手」という女性ミステリ作家にありがちな大きな欠点も抱えており、その欠点の分量込みで、桐野の出世作『OUT』の完全な再現となっている。
(事情を知らない方が本作を『OUT』と無関係と断じているが、桐野は不倫相手と『OUT』を作ったのであり、その創作に至る道筋が本作には書かれている。)
小説家が小説家を主人公にした小説は非常に多く、その大部分が作者の狭い世界の狭さを見せられているようで興ざめなものだが、本作は、その狭さをすさまじい深さで補い、充分に必然性のある激しい作品を作出している。
本作は、桐野の最高傑作には絶対にならないが、次へのステップとして大きな意味がある重要な作品であることははっきりしており、読むべき一冊であることは明らかだ。

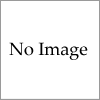

![【薬害の恐れ】子宮頸癌予防ワクチンの危険性[桜H22/7/29] アジュバンド](http://img.youtube.com/vi/832QbV5ajqA/1.jpg)



