
平等院鳳凰堂―現世と浄土のあいだ
寡聞にして、あの鳳凰堂は平等院の阿弥陀堂に過ぎず、
平等院本堂の中尊は大日如来であることは知りませんでした。
一般的に平等院鳳凰堂のイメージは
浄土教の極楽浄土だと思います。
しかし、著者は浄土教というフィルターをはずし、
さらに近代学問によって細分化されてしまった鳳凰堂を
総体的に捉え直すことで、鳳凰堂の真の姿に迫ろうとします。
その過程は、密教と鳳凰堂の関係を読み解くことであり、
五つの謎を挙げ、その謎が順に解かれていきます。
その五つの謎とは、以下の通りです。
第一の謎 主題に定説がない仏後壁前面画
第二の謎 経典を無視した壁扉画の九品往生図
第三の謎 本尊光背にあらわされた雲
第四の謎 朱色に塗られた阿弥陀如来像の胎内
第五の謎 雲中供養菩薩像に墨書された密教尊の名号
一見すると、なにやら難しそうですが、
内容は非常に面白い上、文章もわかりやすいので、
まるで新書を読むが如きにサクサクと読むことができます。
結論を述べれば、平等院鳳凰堂を通じて、
平安仏教を多角的に観ることができる良書だと思います。
仏教、特に密教が大好きな方にお薦めします。

平等院鳳凰堂―よみがえる平安の色彩美
平等院鳳凰堂建立当時の彩色をCGで再現…実に見応えがある。
実際我々が現存する往時の建築物を一見した所で、今では
枯れてしまったその色合いから時間経過の長大さを感じる
のが関の山なのだが、その感覚をこの一冊は楽々と吹き飛ばしてしまう。
この色彩こそは、往時の人々が望んだ浄土の姿なのだろう。
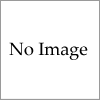
平等院王朝の美―国宝鳳凰堂の仏後壁 (別冊太陽)
別冊太陽の編集方針に感心している読者の一人です。出版社としての矜持が感じられ、丁寧で質の高い出版を続けていく姿勢に共感しています。
本書も同様で、『平等院王朝の美』というタイトルですが、前半の83ページまでは「国宝鳳凰堂の仏後壁」についてあらゆる観点から検証し、その真の姿を写真で提示し、詳細な説明を施しています。平安美術や仏画に関心のある読者が多いとは思われませんし、平等院の観光客もそこまで関心を持って拝観しているわけではないでしょうが、学術的にも価値のある貴重な王朝壁画です。ご本尊の阿弥陀如来が移動した時にのみ目にできる仏後壁でもありますので、今回の出版の貴重さもそれで伺えると思います。
研究者や有識者の文や写真も豊富に掲載してあり、内容も多岐に渡り簡単に解説するのは難しいですが、藤原道長・頼通の求めた極楽浄土という姿を知るのには最適の仏画でしょう。平安の絵師は絵仏師ではないという説も披露してありました。西方浄土が標準なのに、鳳凰堂の仏後壁が北にあるのはなぜか、という疑問も書かれています。顔料や色の本質に迫る調査の詳細も披露してありますので、このような事柄に関心のある向きには堪らないような深い内容だったと思います。
後半のページでは、仏師・定朝の代表作の阿弥陀如来坐像や平等院について、村井康彦氏ほかの貴重な論考が掲載してありました。豊富な写真も載っていますので、その魅力に迫れます。
つい先日、平等院の阿弥陀堂に入ってきて実際拝ませていただいたばかりですので、より関心を持って読了しました。平等院の拝観の前にこれだけの予備知識があれば深いご対面が果たせると思います。ミュージアムの「鳳翔館」には復元図が掲げてありました。







